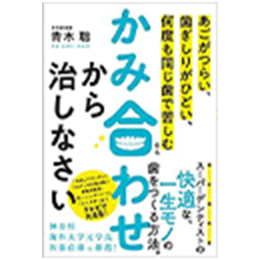Aiming for beautiful teeth
and a comfortable bite
患者さまの笑顔のために
美しい歯と快適なかみ合わせを目指します。
顎運動機能を考慮した矯正・咬み合わせ治療や顕微鏡を用いた精密な処置など、
患者さま一人ひとりに適した総合的な歯科治療を行います。
Concept
私たちのコンセプト

Gnathological Orthodontics and Occlusion Medicine
顎機能を考慮した矯正治療と、医学的に根拠のあるかみ合わせの治療
歯や顎に関する疾患(虫歯、歯周病、顎関節症、歯並び)をまんべんなく診査した上で「総合診断」を下し、その結果に沿って総合的な治療を進めています。
虫歯や歯周病の治療はもちろんのことですが、より良いかみ合わせを作り、快適な生活をしていただくことを目指しています。


Important News
大切なお知らせ
かみ合わせの総合診断について
2023年度
かみ合わせの総合診断に含まれているあごの機能診断は、火曜日または金曜日のみとなっております。
ご希望の方はスタッフにご相談ください。
感染防止対策について
2022年度
青木歯科ではこれまで同様に、器材の滅菌消毒等の感染防止対策を継続して行っております。
患者様には診療ごとの体温測定やアンケート調査をお願いしており、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
HP内、他のページにも動画がありますので是非ご覧ください。
News
お知らせ
-
2024.04.09
4月28日(日)~5月6日(月)まで休診となっております。
7日(火)より通常営業になります。
5月11日(土)は院内セミナーのため休診になります。
尚、休診の期間中は区内の当番医の先生は下記の通りです。
https://shin-shi.or.jp/guide/sos/
何かございましたらaokigd・gmail.comへご連絡ください。
(お手数ですが・の部分を@に変えて送信してください。)
-
2024.03.15
本日3月15日(金)の診療は17時までとなっております。
3月16日(土)は通常通り診療開始致します。
-
2024.03.06
本日3月6日(水)の診療は16時までとなっております。
3月7日(木)は通常通り診療開始致します。
-
2024.03.01
本日3月1日(金)の診療は16時までとなっております。
3月2日(土)は通常通り診療開始致します。
-
2024.02.27
本日2月27日(火)の診療は17時までとなっております。
2月28日(水)は通常通り診療開始致します。
-
2024.02.09
-
2024.02.07
本日2月7日(水)の診療は17時までとなっております。
2月8日(木)は通常通り診療開始致します。
-
2024.02.07
-
2024.01.12
-
2023.12.27
冬季休暇は12月28日(木)~1月4日(木)となります。
1月5日(金)は通常通り10時30分より診療致します。
予約状況により診療時間を短縮する場合もございますのでご承知ください。
-
2023.12.20
明日12月21日(木)の診療は17時までとなっております。
12月22日(金)は通常通り診療開始致します。
-
2023.12.13
本日12月13日(水)の診療は16時までとなっております。
12月14日(木)は通常通り診療開始致します。
-
2023.12.07
本日12月7日(木)の診療は17時までとなっております。
12月8日(金)は通常通り診療開始致します。
-
2023.11.22
冬季休暇は12月28日(木)~1月4日(木)となります。
1月5日(金)は通常通り10時30分より診療致します。
また、1月13日(土)は院内セミナーの為、休診日となります。
予約状況により診療時間を短縮する場合もございますのでご承知ください。
-
2023.11.10
本日11月10日(金)の診療は16時までとなっております。
また11日(土)は院内セミナーの為、お休みをいただいております。
11月14日(火)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.11.07
-
2023.10.04
本日10月4日(水)の診療は13時までとなっております。
10月5日(木)は15時00分より診療開始致します。
-
2023.09.22
-
2023.08.24
-
2023.07.14
本日7月14日(金)の診療は17時までとなっております。
7月15日(土)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.07.05
本日7月5日(水)の診療は16時までとなっております。
7月6日(木)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.07.04
-
2023.07.01
当院はオンライン資格確認について、下記の整備を行なっております。
〇オンライン資格確認を行う体制を有しています。
〇薬剤情報・特定健診その他の必要な情報を取得・活用して診療を行ないます。
〇当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定します。
※令和5年12月31日まで、特例措置に伴い以下の点数を算定します。
【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
1.施設基準を満たす医療機関で初診を行なった場合 6点
マイナンバーカードを利用して受付しなかった場合 もしくは、
マイナンバーカードを利用して受付し、情報提供に同意しなかった場合
2. 1であって、オンライン資格確認等により情報を取得した場合 2点
マイナンバーを利用して受付し、情報提供に同意した場合
3.施設基準を満たす医療機関で再診を行なった場合 2点
マイナンバーカードを利用して受付し、情報提供に同意しなかった場合
-
2023.06.23
本日6月23日(金)の診療は16時までとなっております。
6月24日(土)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.06.07
本日6月7日(水)の診療は15時までとなっております。
6月8日(木)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.05.27
本日5月27日(土)の診療は16時30分までとなっております。
5月30日(火)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.05.24
-
2023.04.14
4月29日(土)~5月8日(月)まで休診となっております。
9日(火)より通常営業になります。
5月13日(土)は院内セミナーのため休診になります。
尚、休診の期間中は区内の当番医の先生は下記の通りです。
https://shin-shi.or.jp/guide/sos/
何かございましたらaokigd・gmail.comへご連絡ください。
(お手数ですが・の部分を@に変えて送信してください。)
-
2023.03.25
-
2023.03.22
3月24日(金)は休診日となっております。
3月25日(土)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.03.02
3月2日(木)の診療は17時までとなっております。
3月3日(金)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.02.22
2月22日(水)の診療は16時までとなっております。
23日(木)は祝日の為、休診日となります。
24日(金)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.02.10
2月10日(金)の診療は17時までとなっております。明日は祝日の為、休診日になります。
2月14日(火)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.02.04
2月4日(土)の診療は15時30分までとなっております。
7日(火)は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.02.03
2月3日(金)の診療は17時までとなっております。
明日は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.01.20
1月20日(金)の診療は17時までとなっております。
明日は通常通り10時30分より診療開始致します。
-
2023.01.12
2月1日(水)、2日(木)、3(金)、4(土)、18日(土)は院内セミナーのため休診となります。
尚、休診の期間中は区内の当番医の先生は下記の通りです。
-
2023.01.05
ホームページをリニューアル致しました。
-
2022.11.01
冬季休暇は12月28日(水)~4日(水)となります。
予約状況により診療時間を短縮する場合もございますのでご承知ください。
-
2022.11.01
-
2022.11.01
-
2022.11.01
カード(クレジット、クイックペイ、ジェイデビット)のご利用は自費治療費のお支払いのみとなり、保険診療の場合はご利用いただくことができません。
Paypayがご利用いただけるようになりました(自費治療費のお支払いのみ)。
2005年から御茶ノ水で診療をしていた青木総合歯科(旧名称)は2017年4月、新宿区西新宿に移転し、医院名称を「青木歯科」と改称しました。


 お問い合わせ
お問い合わせ